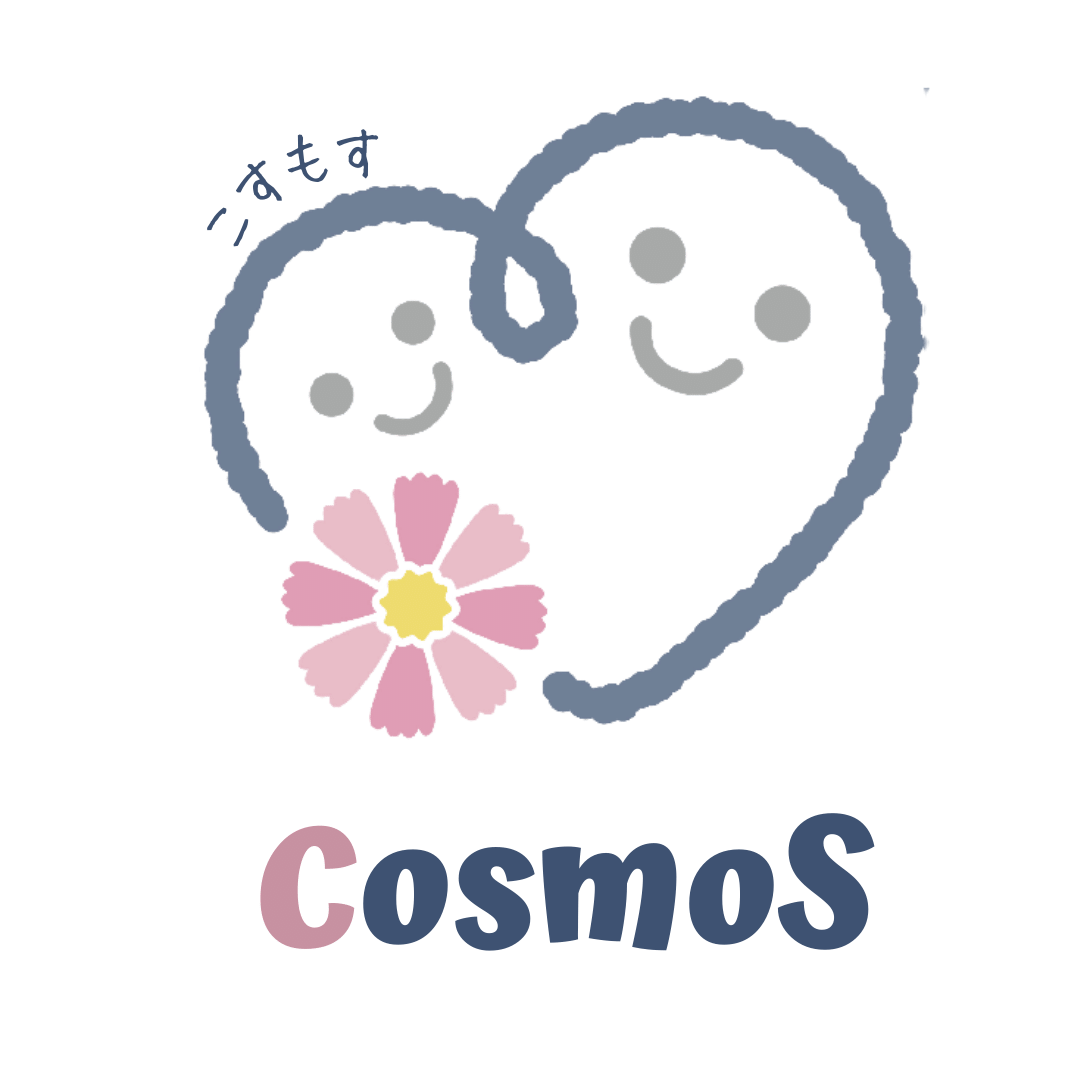1. 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者(児)の活動の自由を制限するものであり、利用者(児)の尊厳ある生活を阻むものとされています。
当法人では、利用者(児)の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、職員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めています。
- 身体拘束廃止の規定
サービス提供にあたっては、利用者(児)又は他の利用者(児)などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者(児)の行動を制限する行為を禁止しています。 - 緊急やむを得ない場合の例外3原則
利用者(児)本人又は他の利用者(児)の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束により心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、以下の切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、家族への説明と同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
| ① 切迫性 | 利用者(児)本人又は他の利用者(児)等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 |
| ② 非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 |
| ③ 一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 |
※ 身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2.身体拘束適正化検討委員会その他の事業所内の組織に関する事項
- 当法人では、身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するために、身体拘束適正化検討委員会(委員会)を設置します。
委員会は年に1回以上開催することとし、特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。 - 委員会の構成員、委員会の責任者は法人代表とし、各事業所より1名選定し構成します。
- 虐待防止委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。
- 本委員会では、次のような内容について競技し、検討結果を従業員に周知徹底いたします。
- 3要件(切迫性・非代替性・一時性)の再確認
- 身体拘束を行っている利用者がいる場合3要件の当該状況を個別具体的に検討し、併せて利用者(児)への心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
- 身体拘束を開始するための検討が必要な利用者(児)がいる場合、3要件の該当状況、特に代替案を検討します。
- やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合、家族、関係機関等との意見交換により調整の進め方を検討します。
- 意識啓発や予防策等必要な事項の確認と見直し
- 以降の予定(研修・次回委員会)
- 議論のまとめと共有
3. 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
- 職員に対する身体拘束適性化のための研修が、本指針に基づき、身体拘束適性化に関する基礎的内容等の適性な知識を普及・啓発することを目指します。
- 実施は、年1回以上行います。また、新規採用時にも研修を実施します。
- 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。
4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
緊急やむを得ない理由により身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者(児)の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適性会員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
(1)3要件の確認
- 切迫性 利用者(児)本人または他の利用者(児)等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がないこと。
- 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2)要件合致確認
利用者(児)の幼体を踏まえ身体拘束適性化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
(3)記録等緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合
次の項目について具体的に利用者(児)・家族へ説明し個別支援計画、計画書・報告書へ記載します。
- 拘束が必要となる理由(個別の状況)
- 拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
- 拘束の時間帯及び時間
- 特記すべき心身の状況
- 拘束開始及び解除の予定
6.利用者(児)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、求めに応じいつでも家族等が自由に閲覧できるよう、当法人のホームページに公表することとします。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する。